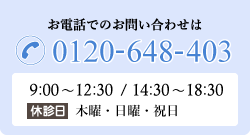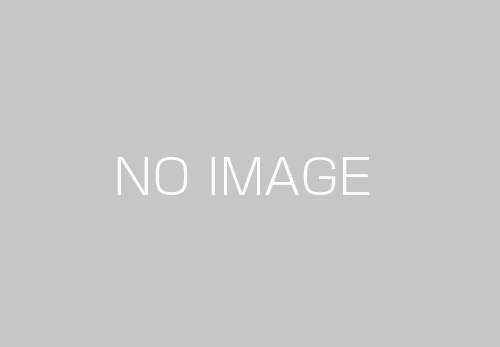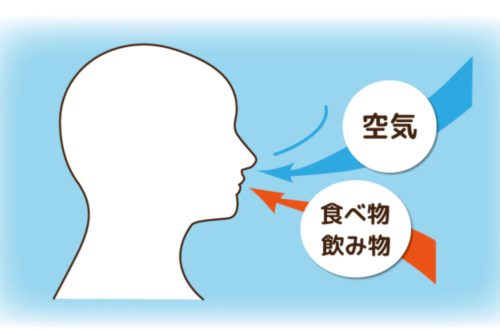2025年も気づけば3月となりました。
少しずつ暖かい日も増えてきましたね!
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
ちなみに、3月4日は「酸蝕歯(さんしょくし)の日」とされています。
みなさん「酸蝕歯(さんしょくし)」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
これは、酸によって表面のエナメル質が溶けてしまった歯のことを言います。
近年、この酸蝕歯が『虫歯』『歯周病』に続いて歯を失う原因として問題になっています。
酸蝕歯の原因は、酸性が強い飲食物などの酸に歯が長時間さらされることです。
通常、お口の中はpH7程度の中性に保たれていますが、エナメル質はpH5.5以下になると溶けやすくなります。
食事をすると、飲食物に含まれる酸や糖質を餌にして虫歯が更なる酸を作ってお口の中が酸性に傾いてしまいますので、この状態が長く続くとエナメル質が溶けだしてしまうのです(脱灰)。
とはいえ、通常は食後に分泌される唾液によってお口の中に残った酸が中和されてpHは元の中性へと戻るため、脱灰されたエナメル質も自然に補修されているのですが、酸性の強い飲食物を摂取したり、だらだらと間食したりすると、この補修の力がうまく働かずに酸蝕歯のリスクが高まってしまいます。
<酸性の強い飲み物・食べ物>
●炭酸飲料 pH2.2~3.5
●乳酸飲料 pH3.5~5.5
●スポーツドリンク pH3~4
●りんごジュース pH3~4
●ビール・赤ワイン pH3.8~5
●レモン pH2.1
●グレープフルーツ pH3.2
●みかん・オレンジ pH3.5~4
●ドレッシング・ポン酢 pH3~4
●醤油 pH4~5
このような酸性度の高い飲食物を頻繁にとっている人は特に注意が必要です。
酸蝕歯は初期段階では症状が出ないことも多いため、ご自身では気づいていない方も多いですが、一度酸によって溶かされたエナメル質は自然ともとに戻ることはありません。
放っておくと、歯が黄ばんだり、表面がデコボコになったり、噛み合わせが悪くなったり虫歯のリスクが上がる等、審美的にも機能的にも問題が生じてしまいますので、早めの対処が重要です。
また、胃食道逆流症など胃や食道の病気、あるいは暴飲暴食といった生活習慣等で、胃酸が逆流する状態が続いていると口の中が酸性に傾くため、酸蝕歯になりやすくなります。
<酸蝕歯の症状>
●熱い飲み物や冷たいものがしみる
●エネメル質が薄くなることで象牙質が透け、歯が黄ばんで見える
●被せ物や詰め物が外れやすくなる
●歯の先端が欠ける
●歯の表面がくぼんだり、穴が開いたようになる
<酸蝕歯の予防と対策>
◎炭酸飲料などの酸性度の高い飲料を長時間にわたって口の中にためない
◎酸性度の高いものを口にしたらお水でうがいをする
◎酸性度の高い飲食物を口にする回数を少なくする
◎唾液の分泌が少なくなるスポーツの後や就寝前は酸性度の高い飲食物を控える
◎毛先の柔らかい歯ブラシを使って優しく歯磨きを行う
ご自身の歯の健康のために改めて食習慣を見直し工夫してみてくださいね。
新年度に向けて歯の定期検診を行っていきましょう!
クボ歯科クリニック